いま旬の若き日本のトップ・プレイヤーたちが一堂に会し、京都でフォーレの名曲ピアノ五重奏に挑むコンサート(2019年11月10日(日)京都コンサートホールアンサンブルホールムラタ)。
本ブログで、北村さんとエール弦楽四重奏団(以降、エールQ)の山根さんへのインタビューをお届けしましたが、今回はエールQのヴィオラ奏者、田原綾子さんにお話を伺うことが出来ました。
前回のインタビューで山根さんと北村さんが「田原さんはフレンドリーで、温かさなどを感じる人」とお話されていましたが、お会いしてみるとその言葉通り、本当に気さくでとてもチャーミングな方でした!
 ――こんにちは!お忙しい中、京都コンサートホールまでお越しいただき、ありがとうございます。さて、関西では過去に何度か演奏されていますが、京都での演奏は初めてですか?
――こんにちは!お忙しい中、京都コンサートホールまでお越しいただき、ありがとうございます。さて、関西では過去に何度か演奏されていますが、京都での演奏は初めてですか?
田原さん(以下敬称略):実は京都コンサートホールは初めてで、来たのも今回が初めてです。同じ京都にあるバロックザールとアルティでは演奏したことがあるんですけどね。私の祖父母が京都在住なので、京都にはよく来ます。
――そうなんですね!京都のどちらですか?
田原:宇治です。また、毎年3月に京都で開催される「京都フランス音楽アカデミー」に参加していたのですが、祖父母の家から通っていましたので、年に1回は京都に来るという感じでした。
――ということは、いま師事されているブルーノ・パスキエ先生とは、京都フランス音楽アカデミーがきっかけで出会われたのですね。
田原:そうです。パスキエ先生に師事したくてパリのエコール・ノルマル音楽院へ行きました(※現在も在学中)。
ヴィオラとの出会い、ヴィオラの魅力
――よく尋ねられることだとは思いますが、改めてヴィオラとの出会いについて、そして田原さんが感じるヴィオラの魅力を教えてくださいますか。
田原:もともとヴァイオリンを5歳から弾いていて、「桐朋学園大学音楽学部附属 子供のための音楽教室」の鎌倉教室に小学校の時からずっと在籍していました。
高校では桐朋女子高等学校のヴァイオリン科に入りまして、ヴァイオリンを一生懸命弾いていたんですが、ちょっと息苦しいところがあったりしまして…。
もちろんヴァイオリンが好きで、音楽が好きで桐朋の高校に入ったんですけどね。
音楽教室に在籍していた頃からずっと、室内楽で色々な人と一緒に演奏するのが楽しくて、桐朋の高校に入ったら室内楽をやりたいと思っていましたので、高校2年生の時に、カルテットを組むことにしました。それが、いまのエールQです。
エールQを組むときに初めてヴィオラを触りました。それまではヴィオラとは縁がなかったのです。でもなんとなくヴィオラという楽器に興味はあったのです。
「ヴィオラを弾いてみたいなぁ」と思っていたので、その時に「山根くんと毛利さんはヴァイオリンで、私はヴィオラ弾く!」って言いました。
「ヴィオラとの出会い」はこの時ですね。
――カルテットを始めた時に、ヴィオラへ転向したのですね。
田原:はい、カルテットを始めると同時にヴィオラを始めました。
当時は独学だったので、メンバーの足を引っ張ってしまっていたと思います。
思うように演奏出来なかったことがあまりに悔しかったので、当時師事していた藤原浜雄先生(※国際的に活躍する名ヴァイオリニスト)に「ヴィオラをしっかり習いたい」と相談しまして、岡田伸夫先生(※ヴィオリスト、著名な海外オーケストラのヴィオラ奏者を歴任)を紹介してもらい、高校3年生の時にヴィオラを習うようになりました。なので、実質的にヴィオラをちゃんと始めたのは高校3年生、18歳の時です。
――エールQで始めた時は自己流だったということに驚きました。
田原:最初は見よう見まねでやっていたのですが、やっぱりヴィオラ弾きが出すヴィオラの音と、自分の弾いている「大きなヴァイオリンを弾いている」音とは全然違いました。どうしたらいいんだろうと思い、色々な方々からアドバイスをいただいたり、演奏会を聴きに行ったりしたのですが、どうしてもわからなかったんです。
岡田先生の下では、本当に基礎から始めました。最初は楽器の構え方や解放弦だけ弾いていまして、「あぁ、こういう風にヴィオラの音を出していくんだな」と学び始めました。
――そういう時間を積み重ねていくうちに、ヴィオラという楽器にどんどん魅入られていかれたのでしょうね。
田原:ヴィオラの魅力は、ヴァイオリンとは違って、何より音色が暖かくて、深みがあるんです。
ヴァイオリンの華やかな音色とか、チェロの包容力のある音の響きなどももちろん大好きで素晴らしいんですけど、ヴィオラは旋律を演奏した時に、ヴィオラにしか出せない、心に響くような独特の音の力を持っているのではないかなと私は思っています。
カルテットなどでしたら、第二ヴァイオリンと一緒に内声を作ることが多い役割を持つのがヴィオラです。
「内声」っていうのは、「内なる声」と書くように、作曲者の内なる声がすべて凝縮されているように思います。
かつて今井信子先生(※日本を代表するヴィオラ奏者)が、カルテットをワインに例えて、「ラベルが第1ヴァイオリンで、ボトルがチェロで、ワインそのものが内声ね」と仰ったことがあります。
それくらい内声は大事な声部なんです。結局ラベルがよくないと手には取ってもらえないですし、ボトルが脆いと中身が漏れてしまいますが、最後は内声が大事なんですよ、と。
私自身、ヴァイオリンは歌って欲しいし、チェロは綺麗にしっかり心強く支えていてほしいです。でも「最後は内声が大切になってくるんだ」というように、強く意識して弾くようにしています。
今回演奏するフォーレもそうですけど、その曲を実際に演奏してみると「ヴィオラが持っている音色を意識して、とても大事に思って曲を書いてくれたな」と思うことが多いです。
ヴィオラ・ソロももちろん素敵なのですが、室内楽では必要不可欠な存在であるということが、ヴィオラの一番の魅力であると感じています。
――たしかに室内楽を聞いていると、ヴィオラが和声の要になっているなと感じることがたびたびあります。
田原:あまりヴィオラがしゃしゃり出てしまうと、それはそれで中身が溢れかえっちゃうような印象を与えてしまいますので、それには気をつけています。
ヴィオラにはヴァイオリンとチェロを上手くつなげる役割を持っていますし、リハーサルをしていても、ヴィオラの人は「今日このメンバーの調子が悪いな」とか「あ、今日は調子がいいな」など、よく考えていると思います。
――今回のフォーレの楽譜を見ていると、ヴィオラの重要さが際立っていますよね。2番は、ほぼ全ての楽章がヴィオラからスタートしているし、1番はほかの室内楽と比べてちょっとヴィオラの役割が違うのかなと思いました。
田原:2曲共に、とてつもない大曲です。私自身、2番は演奏したことがあるのですが、今回はとてもやりがいのあるプログラムを組んでいただいて「頑張らないといけないね」ってメンバーで話しています。

フォーレ作品の魅力、特にピアノ五重奏曲について
――田原さんがフォーレを演奏している時、どういったところに魅力を感じられますか?
田原:フォーレは室内楽や歌曲をたくさん残していますが、和声の進行や、そこから作り出される響きが、本当に精巧に作られているんです。
ラヴェルやドビュッシーは、「いかにもラヴェル!」「いかにもドビュッシー!」っていう感じがしませんか?
でもフォーレは、最初にパッと聴いても、ラヴェルやドビュッシーほどは分かりやすいものではないと思います。宗教的な色が濃い、と言ったら良いのかな。
でもその分、聴けば聴くほど、フォーレの奥深さや味わいが伝わってくるのではないかなと思っています。
個人的に、フォーレの音楽を聴いていると背筋が自然と伸びるような、そんな印象を持っています。
だから今回のプログラムは本当に大変なんですよね(笑)。
――フォーレのピアノ五重奏曲第二番を演奏されたと仰っていましたが、どのような作品でしたか?
田原:4楽章構成なのですが、なによりも第3楽章がこの世のものとは思えないくらい美しくて、演奏していると心が洗われていくような気持ちになります。
それゆえに難しいんですけどね。
1, 2, 4楽章もそれぞれに素晴らしいのですが、3楽章だけ音楽の次元が少し違うような印象を持ちました。皆さんにもこの3楽章を是非聴いていただきたいです。
ただ、演奏される機会があまりないんですよね。
――そうですよね。なぜでしょうね。
田原:ピアノ五重奏曲と言えば、やはりブラームスだったりドヴォルザーク、シューマンなど、そういった作曲家の作品をイメージされる方が多いですよね。
フォーレは内容からみても演奏技術からみても、難しい曲かもしれません。
フォーレのピアノ五重奏曲は、メンバー5人全員が同じ方向性を持って「こういう音楽をこのような表現で、このような音にしたい」という気持ちを持って演奏しないと、フォーレ作品の深さまで到達することは出来ないだろうと思います。
たくさんの深い内容を持つ作品なので、色々なアイディアがメンバー間で生まれますし、皆でディスカッションして納得して、まとめていくことが大切だと思っています。
――そうなってくると大切なものがリハーサルですね。
田原:そうですね。でもリハーサルをする以前に、どういう風に作りたいか、それぞれのヴィジョンがしっかりしていないといけませんね。もちろん全員で過ごす時間も大事だし、一人で曲と向き合う時間も大事なんじゃないかなと思ったりします。
――以前、北村さんと山根さんにインタビューをした際、北村さんが「リハーサルをしっかり出来ないなら、この曲(フォーレのピアノ五重奏曲)は引き受けられない」というようなことを仰っていたのが印象的でした。

田原:この前少し考えていたのですが、リハーサルってお化粧に例えられるなと思ったんです。お化粧をする時、化粧水で肌を整えたり、下地を塗ったりしますよね。それと一緒で、例えば時間がなくて丁寧なリハーサルが出来なかったら、どれだけ本番で濃い演奏をしたとしても、綺麗には見えないんだなと思いました。
リハーサルとゲネプロと本番って考えた時に、本番に向けて、どれだけ良い肌の状態にもっていけるかみたいな(笑)
ゲネプロっていうのは最後の仕上げ。どこまで見栄えが変わったりするか、そういった場がゲネプロです。本番は、もう出来上がったものを最後にどうなるか、例えば誰かと会っている時に表情が華やかだと一層美しく見えるみたいな、そういうふうに考えていたことがありました。
だからこそ、リハーサルはすごく大事で、やっぱり時間をかけないといけない。ゲネプロ、本番に持って行くまでに出来るだけ良い状態に仕上げていかないといけません。
――お化粧に例えられたのはとても面白いと思いました。まさにそのとおりです。肌を整えないと、どれだけメイクしても厚化粧になったり、逆に肌が汚く見えたりしますからね。
それでは次はいよいよ、エール弦楽四重奏団のメンバーについてお聞きしたいと思います。
後編につづく・・・
(2019年4月アンサンブルホールムラタにて)
★公演情報はこちら





-724x1024.jpg)



-724x1024.jpg)
-724x1024.jpg)




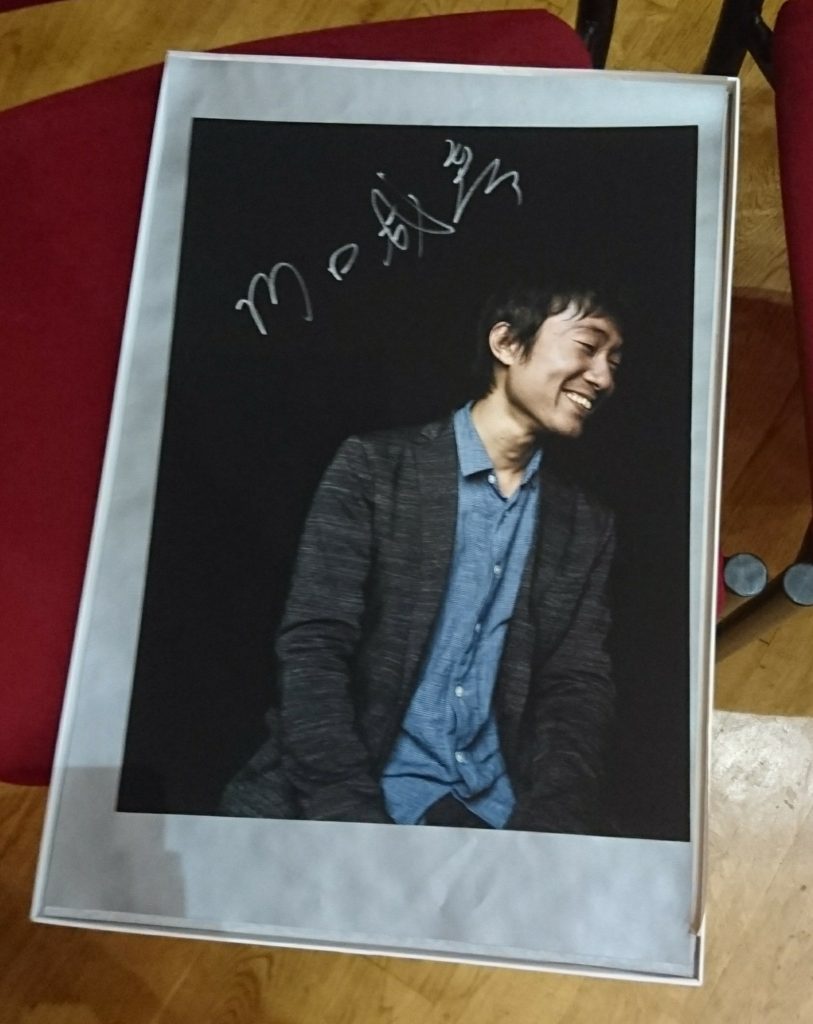


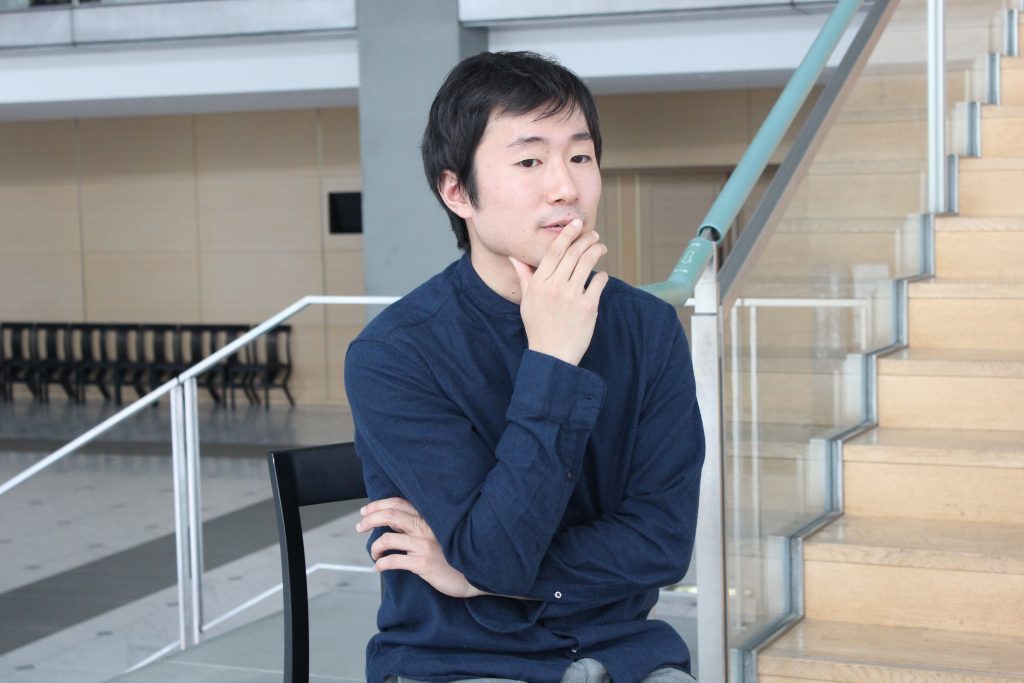

Hikaru.☆-300x200.jpg)













-724x1024.jpg)
-724x1024.jpg)



